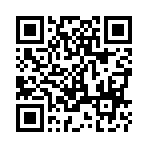2018年03月20日
元祖 丁子屋


しずおか味な店
元祖 丁子屋
江戸時代から積み重ねてきた
素朴で温かなおもてなし
丸子宿は、
東海道で日本橋から21番目の宿場。
丁子屋は慶長元年(1596)、
丁子屋平吉が創業。
自然薯が獲れる時期に
旅人にとろろ汁をふるまいました。
関ヶ原の役に勝利した徳川家康公は1601年正月、
改めて東海道に宿場を設置。
大名の参勤交代制が確立すると
宿場は一段と整備され、
元禄年間には庶民が旅に出かけるようになりました。
「梅わかな 丸子の宿の ととろ汁」は1691年、
松尾芭蕉が詠んだ句。
とろろ汁は、
丸子宿の名物と認められました。
1802年、駿府出身の作家・十返舎一九は
「東海道中膝栗毛」を出版。
丸子宿では、
茶屋の夫婦げんかで、
弥次さん喜多さんがとろろ汁を食べ損なう場面を
書きました。
1834年、浮世絵師の歌川広重は
「東海道五十三次 保永堂版」丸子宿で、
庭先に梅が花咲く茶屋で、
二人の旅人がとろろ汁を味わう姿を描きました。
丸子宿には、
とろろ汁をめぐる庶民文化が形成されました。
丁子屋では、
江戸時代の味と雰囲気を体感していただこうと、
大鑪の旧家・近藤家のわらぶき屋根の古民家を移築。
土づくりからこだわって栽培した
滋味豊かな自然薯に、
自家製の優しい味わいの白味噌と
自家削りした香り立つ鰹節で作った味噌汁、
玉子を合わせて、
味わい深いとろろ汁を作ります。
そして、昔の家に帰ってきたような、
懐かしくて温かみのある雰囲気で、
お客様をおもてなししています。
十三代店主
柴山 馨さん
メニュー
とろろ定食 1440円~
揚げとろ 900円
焼きとろ 760円
価格は税込
営業時間
11時~19時
木曜定休
※月末のみ水曜・木曜連休
施設
座敷席 250名
駐車場 バス8台 普通車80台
所在地
静岡市駿河区丸子4-10-10
電話054-258-1066
https://www.chojiya.info
https://www.facebook.com/chojiya.tororo
この記事は、2011年6月の取材時の内容です。
料理の内容や料金を改定している場合があります。
ホームページなどで、ご確認ください。
参考:2017年9月号掲載記事

広重が描いた茅葺きを
今の時代に残したい
東海道丸子宿
丁子屋
14代目
柴山広行さん
丁子屋は、
浮世絵に描かれた店の中で、
唯一現役で営業する店です。
その象徴は、
広重の絵を思い浮かばせる
「茅葺き屋根」。
丁子屋のシンボルであり、
東海道の宿場のシンボルです。
しかし、その維持には
20年ごとに1千万円以上かかるなど
継続がむずかしくなっています。
前回の修繕から約40年がたち、
老朽化が激しく、
このまま放置していては、
修繕すること自体が
むずかしくなってしまいます。
丁子屋の歴史を振り返るときに、
私自身とても大切にしている
エピソードがあります。
昭和45年。
時代は高度成長期。
古い家を取り壊し、
近代的な建物に替わる中、
じーちゃんは
「丁子屋には何にも替え難い歴史がある」
という信念のもと、
広重が描いた「茅葺き屋根」を
移築、復活させたのです。
だからこそ、
じーちゃんから受け継いだ風景を、
14代目の私も守り続けたいのです。
茅葺き屋根職人は
現在、全国で200人程度。
加えて高齢化により、
技術の伝承が危ぶまれています。
茅葺屋根を後世に残していくためにも、
葺替え、保存をしていく必要があります。
今回のプロジェクトには、
東海道を盛り上げている宿場の方々に
ご協力いただいています。
東西の宿場を繋げることは、
東海道の未来を守ることなのです。
私は
東海道の歴史が未来へ継承されるように、
責任を持って次の世代に
バトンを届けたいと思います。
広重が残した風景を未来に繋ぎ、
東海道の宿場を繋げ、
盛り上げていくためにも、
茅葺き屋根の修繕を行います。
皆様の温かい応援をお願い致します。
クラウドファンディング
「Ready for 丁子屋」はこちらへ。
https://readyfor.jp/projects/tororotokaidochojiya
おかげさまで
目標金額10,000,000円のところ、
404名の支援者の皆様から
総額11,227,000円の支援を
いただくことができました。
厚く御礼申し上げます。